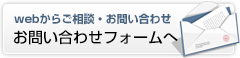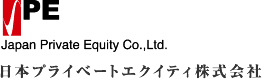コラム “志・継・夢・承”
|
2025年 |
-
2025年11月 Vol.74“30番目の卒業生” と “36の物語”
-
2025年10月 Vol.73続・“19番目のカルテ”から思うこと
-
2025年9月 Vol.72“19番目のカルテ”から思うこと
-
2025年8月 Vol.71後継者不在・・・ 相談相手をみつけた!?
-
2025年7月 Vol.70“経営寿命”と“経営者寿命”
-
2025年6月 Vol.69足し算を掛け算に
-
2025年5月 Vol.68昭和100年の桜
-
2025年4月 Vol.67名は時代を映す鏡
-
2025年3月 Vol.66“買収”ではなく“投資”
-
2025年2月 Vol.65忘れないでいること
-
2025年1月 Vol.64開かれる 2025
“30番目の卒業生” と “36の物語”Vol.74 |
|
コンビニの前に「年賀はがき販売」ののぼりが立ち、お歳暮やおせちの宣伝が目立つようになると、今年ももう終わりかと急き立てられます。 1年があっという間に感じられるのは、季節感のせいだけではなく、年を重ねると日常に新鮮な体験や記憶に残る出来事が減ったからとか、脳の情報処理速度が変わって時間の流れに敏感でなくなったからとも言われます。“ジャネーの法則”は、「生涯のある時期における時間の心理的長さは年齢に反比例する」として、5歳の子どもの1年は「人生の1/5」ですが、50歳の大人にとっての1年は「人生の1/50」と、自分の人生全体に対しての比率が小さくなるので相対的に短く感じるという説を唱えています。 私事ながら、事業承継ファンドを運営する会社を始めてから、先日、25周年を迎えました。さすがに33歳から始まり58歳になるまでの25年は“25/58”ですから長く感じます。この間、オーナー経営者からファンドに事業を託していただいた中小企業は全国で36社。株式と経営を引き受け、社員の方と一緒によりよい会社にして次の世代につなぐというファンドの仕事は「36の物語」を綴ってきたようでもあります。 そして、ファンドには期限があり、必ず、また次の誰かに資本と経営を承継します。ファンドが投資先を次に承継することを“EXIT”といいますが、私は“卒業”と言い換えています。そして、先日、JPEからの30社目の卒業生を送り出しました。 この25年で卒業の形も様々となりました。“卒業生”となった30社のそれぞれの“卒業”の形は「M&Aで事業会社に」が17社、「ファンドに譲渡」が3社、「経営陣が地域の銀行や地域ファンドとともに自社買収(MBO)」が9社、「株式上場」が1社となっています。ファンドとともに過ごす時間を経て、それぞれの会社に合った“卒業”の形が見えてきます。 「36の物語」は、オーナー経営者が書いてきた30頁(年)、あるいは、代々で100頁を超えようかという物語の続きに、ファンドがほんの3~7頁を書き継ぐようなものです。でも、この数頁があることで、物語はまた30頁、50頁と続いていきます。自分が書いてきた物語の続きを誰にどう書き継いでもらうかは、経営者にとってもファンドにとっても難しい課題です。 “ジャネーの法則”に則れば、経営者にとってのこれからの1年、5年はますます短く感じるはずです。そして、会社にとっての1年も、経営環境の変化が激しい今、密度の濃く、短いものになるはずです。 急かされるのが好きな方はいないでしょうが、時代は、経営者にもっと歩みを“速める”ように、意思決定や決断を“早める”ようにと、急かしているです。 以 上 |
| <真> 2025年11月 |
続・“19番目のカルテ”から思うことVol.73 |
|
もう少しだけ、“19番目のカルテ”から思うことを・・・。 今、全国で働く医師は約32万人。その多くが、目の前の仕事に追われて余裕がない、ゆえに一人でも多くの患者さんの病気を治すことに専念するものの、ひとり一人の心に寄り添いきれていないのではないか、“19番目のカルテ”では、こうした理想と現実の間で葛藤を抱える医師の姿が描かれています。 専門医のこうした懸命な姿が、例えば、地域金融機関のいわゆる“ソリューション”部署の担当者、現場の支店長や融資担当、M&A仲介の担当者、顧問税理士といった、地域で事業承継問題に携わる専門家の方と重なります。みな、各々の立場や責任、経験の下に中小企業経営者に助言や提案をしてくれますが、兼務多忙、組織優先、数字重視等々、専門医と同じような葛藤を抱えながら日々奔走しています。 中小企業が安心してM&Aに取り組めるようにと2021年8月に設けられた『M&A支援機関登録制度』に登録する支援機関は、本年9月22日時点で法人2,321件、個人事業主705件。その内訳はM&A仲介専門業者が707件と最も多く、コンサルティング会社、税理士、M&A専門業者(FA)、中小企業診断士と続きます。ただ、M&A仲介業者にとって親族内承継はビジネスの対象ではないですし、士業の多くの方はM&Aの実務経験はなく、それぞれの専門領域のなかで対応する専門医と同じ境遇といえます。 また、医療の骨格を成す「制度」でも、例えば、どれだけ丁寧に“問診”をしても診療報酬にはほとんど反映されないのが現実です。事業承継でも、無報酬で丁寧に相談に応じてくれる専門家がどれだけいるでしょう。もちろん、事業承継では、公的な“無料相談窓口”である「事業承継引継ぎ支援センター」が全国48ヶ所にあり、各センターの相談員は、オーナー経営者や後継者候補からの事業承継に関する相談に対して様々な支援や橋渡しを行っているので、まさに“事業承継の総合診療医”がいるといえます。相談員の人数こそ公表されてはいませんが、全国のセンターの相談者数は2024年度で23,540者と2011年度の開設以来、年々伸びており、累計では15万者を超えています。 一方で、今、全国で働く総合診療医はわずか1,000人ほどということです。疾患と病をもつ人に寄り添い、その心理状態や生活背景など言葉にできない心情も鋭く的確に読みとって、豊富な医療知識に基づいた分析や判断力で病名を特定、最善・最適な治療に導くのが、“総合診療医”。まさに、事業承継の現場にも、こうした心と技術、知見をもって“人を診る”ことができる“総合診療医”がこれからもっと必要です。 以 上 |
| <真> 2025年10月 |
“19番目のカルテ”から思うことVol.72 |
|
猛暑も終盤ですが、どうも体調がすぐれないなというのを夏の疲れだと決め込んでいませんか? 日本の医療が進歩するなか、診療科も細分化が進み、今では、内科、小児科、精神科、脳神経外科、救急科など19の基本領域に専門分化されています。 最近、TVで“総合診療医”をテーマにした『19番目のカルテ』というドラマがありました。 この「総合診療医と医療の現場」の話が、今の「中小企業の事業承継問題の現場」の話と重なって見えるのです。事業承継に悩むオーナー経営者、課題解決に奔走する専門家、企業の存続を支援する地域と行政等、それぞれの関係当事者の姿が、地域の医療の現場と重ります。 また、重なるのは当事者の姿だけではありません。例えば、医療における“問診”は、全ての医師が行う基本であり、診断の7割は問診で決まるそうです。 事業承継でいうなら、若い頃と同じようにはいかない心身の衰え、身体を襲う突然の病気やケガが「Bio」。家族に心配かけたくない、自分自身の人生を見直したい、人として親として…といった個人の想いが「Psycho」。そして、社員や顧客、取引先といった社会に対しての経営者としての責任や使命が「Social」といえるでしょうか。事業承継も、この3つの要素からオーナー経営者という“人”を、そして、もちろん“会社”も総合的に“診る”必要があります。 事業承継の現場の“問診”も、徳重先生と同じように“病気(=課題となっている事象)”だけではなく“人”を診て、オーナー経営者の心理や行動から判断して最善の解決策を見つけ出し、正しい解決策へ導くことが求められます。 『あなたの話を聴かせてください』が、徳重先生の決め台詞です。事業承継という課題に向き合う現場も同じはず、きっとこの一言からすべてが始まります。 以 上 |
| <真> 2025年9月 |
後継者不在・・・ 相談相手をみつけた!?Vol.71 |
|
『年商5億円の中小企業のオーナー経営者です。60歳になりました。後継者不在なのですが、今の事業をどうすればいいでしょうか?』 『ご相談ありがとうございます。年商5億円の事業を築かれ、60歳を迎えられたとのこと、まずは長年のご経営、本当にお疲れ様です。後継者が不在の場合、今後の事業承継については早めに“選択と準備”を始めることが重要です。大きく分けて、以下のような選択肢が考えられます・・・』 『誰に相談すればいいかわからない』というのが後継者不在のオーナー経営者の共通の悩みです。であればと“Chat GPT”に相談してみたところ、人間以上に優しい労いの言葉から始まる回答が返ってきました。 日本経済新聞社が四半期毎に実施している、国内主要企業の経営者を対象とした「社長100人アンケート(6月)」で、『生成AI(人工知能)を使う頻度は?』という質問に対して39.8%が『毎日』と答え、使途(複数回答)は『言語の翻訳』55.9%に続き、『企画等のアイデア出し』が45.1%と、生成AIは、日本の錚々たる企業経営者の頼れる相談相手になり始めているようです。 ちなみに、冒頭のChatGPTの回答は、選択肢として、『社外への承継(M&A)』『社内への承継(従業員承継)』『ファンドや専門会社との連携』の3つを挙げると同時に、会社に十分な利益が出ておらず、買い手も見つからない場合には、最後の選択肢として、従業員や取引先への影響が大きいので慎重な対応が必要だが・・・という但し書きの下に『法的整理・自主廃業』も挙げ、各選択肢のメリットや具体的な方法、課題についての説明が続きました。 また、今すぐに取りかかるべきこととして、
そして、最後に、『必要であれば、従業員数、業種・地域、利益水準、オーナーの希望(完全引退か、数年関与か)、借入や資産状況等がわかれば、より具体的な選択肢も整理できます。』、『ご希望があれば、無料で使えるM&A支援サービスや地域ファンドなどもご紹介できます。どうされたいお気持ちが一番強いでしょうか?』と締め括ります。 ChatGPTの回答に違和感はなく、なかなかやるな!と思いつつ、でも、実体験から得た行間は語れないだろうという負け惜しみを飲み込んで・・・ P.S こちらもお忘れなく・・・ 以 上 |
| <真> 2025年8月 |
“経営寿命”と“経営者寿命”Vol.70 |
|
『横断歩道を渡ろうとしたら青信号が点滅!ダッシュできる年齢って何歳までだと思う?』 この質問に対して、20代は『41歳2ヶ月』と答え、60代は『61歳7ヶ月』と答えました。 生活寿命は、その行動をする動機がなくなるタイミングのイメージなので、必ずしも体力や気力が理由ではなく、個人の嗜好や生活習慣、価値観、家族や社会との関係などにも因り、世代や性別、調査した時代でも変化しています。 例えば、他には・・・
ユニークな生活寿命が60以上も並びます。 ということで、であれば、“経営者ならでは”の寿命として、『経営寿命(あくまでも造語です!)』があってもいいのかとひねり出してみました。 例えば・・・
など、過去に出会った経営者や自分自身も(?)含めて振り返ると、意外と、どんどん思い浮かびます。 なかには、それで経営者をしていて大丈夫?みたいな寿命もありますが、それも現実です。でも、これらの「経営寿命」のいくつかを迎えていたならば、それはさすがに「“経営者”寿命」が尽きる時かもしれません。 『自分が経営者の責を果たせると思う年齢は何歳までですか?』と「経営者寿命」を問いかけながら、「経営寿命」と「経営者寿命」についてはこれからも考え続けようと思います。 以 上 |
| <真> 2025年7月 |
足し算を掛け算にVol.69 |
|
今年ももうすぐ折り返しですが、M&Aは相変わらず活況です。 最近話題のM&Aを挙げると、まず、7月に国内小売業のトップ10にはいる売上高1.2兆円の巨大流通小売グループが誕生します。大手ディスカウントストアのトライアルホールディングスが、総合スーパーの西友を買収しました。 この2社、『地方本社・スーパーセンター・郊外出店・IT祖業・DX駆使・318店舗』×『三大都市圏・総合スーパー・プライベートブランド展開・毎日低価格・244店舗』という組み合わせです。西友は、2008年にアメリカ小売最大手のウォルマートがM&Aで子会社化したものの売却して撤退した経緯があるなか、今回、ウォルマートを目指すと標榜して成長を遂げてきたトライアルHDが、ウォルマートができなかったことに挑戦するという絵となります。 また、外食業界では、大手外食チェーン「すかいらーくホールディングス」による「資(すけ)さん」のM&Aも話題になりました。 この2社は『全国チェーン・ファミリーレストラン・グループ2,996店舗』×『北九州・うどん・ソウルフード・ローカルチェーン・74店舗』という組み合わせです。企業規模こそ違え、店舗展開、食材の共有や配送効率化による原価低減等のメリットが双方にあります。 この2つのM&Aで、売り手、買い手となった4社のうち、トライアルHDと資さんは、いずれも「福岡県が本社の地方発企業」という共通点があります。 西友やすかいらーくという、全国的に知名度の高い会社と組むことで事業展開も日本中に広がります。いずれ、『資さんって北九州の会社だとは知らなかった』『西友って九州の会社のグループなんだ』と言われるようになるのでしょう。 また、この4社のうち3社には「ファンドが株主になっている時期がある」という共通点があります。 M&Aは、2つの会社が一緒になるという“足し算”ですが、お互いのノウハウを移植する、意識を変える、相乗効果を出すことで“掛け算”にもなります。そして、どちらが買った、どっちが売ったという立場は関係なくなり、対等に掛け合うことができれば、不可能と思えたことが可能となります。 「2+2=4」も「2×2=4」も同じ、でも、「3+3=6」だけど「3×3=9」。足し算ではない、掛け算の答えは、まさにM&Aの妙味、今後、この4社がどう変わっていくのか楽しみです。 以 上 |
| <真> 2025年6月 |
昭和100年の桜Vol.68 |
|
お花見の季節が終わり、例年であれば、近所の桜並木が新緑の並木道に変わるはずが、今年は桜の木の伐採が始まりました。見た目にはわからないものの、つい先日まで咲き誇っていた桜も樹齢50年を超えた老木で、幹の芯は蝕まれ、倒木の危険があるからとのことです。約1キロにわたるソメイヨシノ150本のうちの60本が伐採されて新しく植え替えられる予定です。 桜の寿命は、百年千年というイメージでしたが、品種によってかなり違い、原種の山桜の寿命は200~300年と永く、特にエドヒガンザクラの樹齢は1000年、日本最古の桜は樹齢2000年ともいわれています。一方、目にすることの多いソメイヨシノは、江戸時代末期に交雑して生まれた品種で成長は速いものの寿命は短くて約60年、永くても100年ということで人間の寿命に近い感覚です。 ただ、何年か前に伐採された桜の木の切り株の脇から、『まだ生きているぞ!』と言わんばかりに勢いよく枝が伸びていました。これは“ひこばえ(孫生)”や“萌芽(ほうが)”と呼ばれ、植物の上に伸びるエネルギーが脇の芽の成長にまわり、新しい芽が伸びてきたものです。自然の森で、樹齢の古い木や倒木がこうして新しく若い木へと生まれ変わっていくのが“萌芽更新”です。永い年月をかけて自然界で繰り返されることで、森や山の世代交代が進みます。萌芽は、既に地面に根を張った切り株を土台にして水を吸い上げるので、種から育つより、また苗木を植えるよりも安定して成長し、森林が速く育ちます。木や森は、こうして自らの世代交代や再生の方法を身につけています。 自然とはすごいものですが、それは、人間の組織のようでもあります。ただ、知恵を持ち過ぎた人間は、いろいろなことを考え過ぎるので、躊躇したり、先送りし、変われないでいるのが悪いところかもしれません。 ところで、今年は“昭和100年”。1926年12月25日から始まった昭和元年(大正15年)から100年目です。最近は、昭和世代、平成世代、令和世代など年号で価値観や行動慣習をひとくくりにしがちですが、一度、みな“昭和”という同じ線の上に置いてみるとわかりやすく、また違って見えてくるものがあります。 今年の新入社員の多くが生まれた年が「昭和77年(平成14年)」といえば、自分との差や全社員のスタートラインを再認識できます。ちなみに、前回の大阪万博の開催は「昭和45年」。平成元年は「昭和64年」、令和元年は「昭和94年」です。 組織の新陳代謝や世代交代のため、西暦では見えない、“昭和100年”という点の上に立ち、昭和120年、150年を見据えた線の上で、人間なりの“萌芽更新”を考えるには今が絶好のタイミングです。 以 上 |
| <真> 2025年5月 |
名は時代を映す鏡Vol.67 |
|
今春の新卒・新入社員の多くが生まれた年の2002年(平成14年)年の名前ランキングの上位は「翔太・翔・大輝」「美咲・葵・さくら」というデータがあります。みなさんのまわりにもいらっしゃいますか?さらに、最近は、フリガナなしでは名前が読めない時代となり、まさに、名前は“時代を映す鏡”です。 会社の名前も同じで、新年度の4月1日に社名変更した上場企業があります。「YUSHIN(ユーシン精機)」「TANAKEN(田中建設工業)」「AIRMAN(北越工業)」「DAIKO XTECH(大興電子通信)」など、傾向としては、引き続き、グローバルでの認知度向上を意識してアルファベットやブランド名に変更した会社が多く挙げられます。 また、事業領域が広がって、必ずしも社名と事業内容とが一致していないことから、祖業や本業を社名から外したのが、「ユキグニファクトリー(雪国まいたけ)」や「TOYOイノベックス(東洋機械金属)」です。先日、NTTも社名変更すると発表しました。実は、まだ正式社名は「日本電信電話」だったようで、5月決算発表時に新社名を公表、6月の定時株主総会で決議するとのことです。どういう社名になるのかと関心は高まります。 時代や環境の変化に対応して、各社の事業そのものが変容しているので当然と言えば当然の流れです。一方で、中小企業はどうでしょう?まだ漢字表記や創業オーナーの名字が社名といった会社が多く、社名変更への積極的な動きは感じません。 会社名で何をやっている会社かがわかるのは昔の話で、これからは、名前に縛られずに変わっていく、世界へとはばたいていくことを、できることなら社名でも示し、人材採用や社員の意識改革にもつなげたいという中小企業も少なくありません。ただ、やはり、いざ社名変更をするとなると『コストや手間を考えたら無理』『業界や顧客に浸透しているから』『創業一族に配慮すべき』などといった意見が大勢を占め、誰かが強く主導しないと実現できないというのが現実でしょう。中小企業が、よりダイナミックに事業も意識も変えていくなら“事業承継ブーム”ならぬ“社名変更ブーム”が起きてもいいはずですが、その実現には、さまざまな“壁”があります。 名は体を表し、名は時代を映す鏡。オーナー企業にとっての社名変更は、オーナーの会社ではなくなる第一歩であり、事業承継にいざ踏み出そうという時のための布石とも言えます。ゆえに、そう簡単にできることではないとしても、新しい社名に想いを馳せてみるのもいいのではないでしょうか。その延長線上には、将来の会社のあるべき姿や事業承継に向けた絵姿がぼんやりと浮かんできそうです。 以 上 |
| <真> 2025年4月 |
“買収”ではなく“投資”Vol.66 |
|
2025年2月の日米首脳会談でトランプ米大統領は、日本製鉄によるUSスチールの買収計画について『買収ではなく投資』とコメントしました。さすが、実業家でもあるトランプ大統領らしく、光の当て方次第で“見えているもの”をわかりやすく変えると同時に、各当事者の“得られるもの”が大きく変わりうる状況へと導きました。 真意を読み取るためにも発言の原文をたどると、 つまり、日本製鉄は、USスチールに対して『outright purchase(完全な買収)』はできないが『invest “heavily”(多額の投資)』は許される、USスチールが米国企業であり続けることを前提に日本製鉄がたくさん出資をして協力関係を構築するのはいいということになります。 この似て非なる『買収』と『投資』の違いは、経営権(株式の過半)をとるかどうかの違いです。その結果として、
といったことが変わるといえます。 既存株主から過半の株式を買い取って子会社化するという『買収』であれば、経営のすべてを掌握できます。もちろん、日本製鉄は、買収にあたり雇用維持や将来の設備投資、役員選任等での現地中心の経営を約束すると提案していました。しかし、将来、経営環境が変化した際にすべてを決めて変えられるのは、やはり“株主(親会社)”です。『投資』でマイノリティ(少数)の株主になるだけでは、いざという時に成すすべはありません。せいぜい株主間契約や覚書を取り交わして、別途、決め事をしておくかです。ゆえに、日本製鉄からすれば、経営権を握らないで多額な資金を投下することが自社にとってメリットや意味のある投資となるか?が判断基準になってくるでしょう。 さて、この『買収ではなく投資』、あるいは『投資ではなく買収』という選択を巡る思考は、企業規模の大小を問わず、中小企業やスタートアップ企業の経営者がM&Aや事業承継、資本戦略を考える際にも十分に参考となり活用できるものです。 “株主”“経営”“会社”という観点から、『売却か?資本提携か?』『今、オーナーとして株式売却益を実現したいか?会社で資金調達が必要か?』『経営は全て任せるか?株式売却後も社長として続投したいか?』『会社にとって一番必要な経営資源を確実に得ることができるか?』といった判断材料をベースにして、“譲れること“と”譲れないこと“を考えていくと、それぞれがとるべき、今後のM&A戦略や事業承継への道筋が見えてくるはずです。 以 上 |
| <真> 2025年3月 |
忘れないでいることVol.65 |
|
一年を通して、年末年始の1月もしくは12月は、亡くなられる方が多い月という統計があります。人の命や生死にかかわる仕事といえば、医療従事者の方をはじめ、葬祭、介護等がすぐ思い浮かびますが、意外と、金融業である「事業承継ファンド」も例外ではありません。事業承継ファンドの仕事である『中小企業のオーナー経営者が保有する全株式を譲り受け、経営を委ねられ、会社を継承する』というプロセスは、会社の経営の行く末だけではなく、オーナー経営者のこれまでの人生やこれからの人生も含めた“人生そのもの”に関わるものです。 “事業承継”は、オーナー経営者が“死生観”をもってはじめて考えられることであると思っていますが、ゆえに、一生のうちでも終盤、つまり、高齢になってから動き出すことが多いので、当然、病や死にまつわる話も少なくありません。これまで出会ったオーナー経営者の方でも、余命宣告されたことで事業承継に動かれた方、会社をファンドに託した後に程なく天に召された方、株式譲渡契約の締結目前で泉下の客となられた方もいらっしゃいます。生死を前にすると、“オーナー経営者”という肩書を外した一人の人間として相対することとなり、当たり前ですが『同じ人間なんだな』と思いながら喜怒哀楽をともにすることとなります。 事業承継ファンドの仕事として、オーナー経営者との間で会社を“託す・託される”というやりとりをするなかで、病や寿命という“人としての一生”に向き合わざるをえなくなったときには人は何とも無力であり、“できること・できないこと”の“できないこと”ばかりで空しくなります。そして、振り返ると“できたこと・できなかったこと”の“できなかったこと”が多くて、もっと何かできたのではと悔やまれます。 でも、ずっと一緒に生きられるわけもなく、ただ見送ることしかできないのなら、残された人間や託された自分たちにできることは、出会えた奇跡に感謝し、忘れないでいること、覚えていることです。オーナー経営者が、社長として歩んできた道や人として生きてきた証、作ってきたもの、愛してくれたお客さんはしっかりと残っています。 そして、オーナー経営者が築き上げてきた実績や功績、その結晶ともいえる“会社”はもちろんですが、日々、人として、さりげなく交わした言葉、握手した手の温もり、最後に手渡してもらったコンビニ弁当・・・そうした光景をふと思い出し、たとえ永遠はないにしても、忘れずにいたいです。事業承継ファンドという仕事は、そうした他愛もない日常も大切に想いながら、経営に取り組むことで成り立っていると考えています。 最後の最後まで経営者として頑張って人生を全うされた故人への敬愛と感謝の想いを天に届けるため、今、唯一できることは、“忘れないでいること”です。 以 上 |
| <真> 2025年2月 |
開かれる 2025Vol.64 |
|
1月11日の“鏡開き”で正月気分も一区切りですが、鏡餅を“割る”とは言わずに、末広がりを意味する“開く”と言うのは日本語ならではの表現です。そして、2025年の日本は、企業の大小を問わず、“開かれる”ことを求められる1年となりそうです。 2024年は、国境を越え、想像も超えた、大型M&Aが話題になりました。例えば、「日本製鉄によるUSスチールへの買収計画(2兆円規模)」や「カナダのコンビニ大手アリマンタシォン・クシュタール社からのセブン&アイ・ホールディングスへの買収提案(7兆円規模)」、「日本生命の米系生保レゾリューションライフの買収(1.2兆円)」等が挙げられます。日本製鉄やセブン&アイHDの案件は、越年して、2025年もその展開から目が離せません。 また、「KKRとベイン・キャピタル(いずれも米系ファンド)による富士ソフトの争奪戦」「ベネフィット・ワンへのエムスリーと第一生命による国内企業同士のTOB合戦」等、会社を買う、買われる、奪い合うことが市場で繰り広げられ、買い手も異業種や同業もしくはファンドが突然現れるなど、ターゲットとなった企業の経営陣が好きも嫌いも関係ない“同意なき買収”が当たり前になってきました。 現状に甘んじている、あるいは、ほどほどの成長で満足しているとみなされる上場企業には、株主や市場からさまざまな圧力がかけられ、選別が始まり、決断が迫られています。 こうした資本市場の大きなうねりは、中小企業にとっても、主要取引先がM&Aしたりされたりするなど、いつどういう形で自分事となるかわからず、もはや傍観者ではいられません。例えば、日産自動車とHONDAの経営統合にあたり、両社と取引のある企業は重複を除いた単純合計で23,440社に達し、そのうち、売上高10億円以下の中小企業が約15,000社とされています(東京商工リサーチ調べ)。 上場企業が株主から変革と株主価値向上を迫られるなか、未上場企業も『今のままでいい』と許される状況にないのは確かです。未上場企業であっても“開かれた会社”であることが当たり前”という意識で経営を進めていかなければ、未来はありません。 2025年、上場企業も中小オーナー企業も“資本のありかた”を根本的に見直すことが求められる一年となりそうです。 以 上 |
| <真> 2025年1月 |